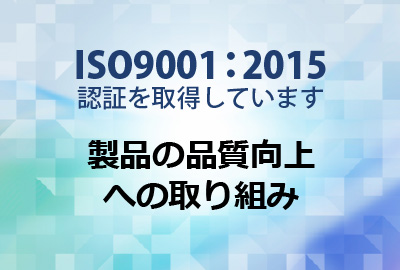当社は時々、鋳物の溶接を引き受けます。
でも、全部が全部できるわけではありません。
毎回書いていますけど(言い訳っぽい)、出来ない鋳物があります。
それはエンジン回りの部品、強度が必要な部品(安全上の理由)、油が染みている部品、高温にさらされた部品、鉄ではない鋳物(亜鉛合金鋳物など、磁石にくっつかないもの)は溶接が出来ません。
幾つも失敗しました。
(失敗してしまった皆さんごめんなさい。)
ブログに書いてあるものは辛うじて出来たケースです。
今の世の中、買った方が安いものもあります。
でも、思い出の品だったり、大切にしていたものだったり、使えなくても元の形状にしてほしい、という案件は出来る限り引き受けるようにしています。
その理由の一つは、当社が運営できているのは、得意先や仲間や社員など、周りのお陰だということ。
ですので、そこで培ってきた知識や技術を少しでも広く世の中に還元できればと思っているからです(大袈裟な話ではないです)。
今回はルクルーゼのお鍋の取手が破損した案件。
これと似たようなものを以前修理しました。
今回、修理の依頼の写真を拝見して「デジャブ?」と思うほどドキッとしました。
それがこれです。

ポッキリと取れてしまっています。
でも、こういう破損は意外と簡単です。
何故なら、破損した断面同士がぴったりと合うからです。


こんな感じにぴったんこ。
確認できれば、作業開始です。

溶接はTig(Tungsten inert gas)溶接で行います。

溶接する部分は琺瑯(ホーロー)を剥がします。
これをちゃんとやらないと溶接時にブローホールやピンホールの原因になります。
そして、それと同じくらい大事なのが「アース」する場所。
溶接は「アース」が取れないとアークが出ません(プラスとマイナスということ)。
普通に溶接するときは定盤全部がアースに繋がっているのでいいのですが、化粧板や表面処理してあるものは、アースの場所を考えないと取り返しのつかないことになります(変なとこにアース痕がついてしまうと大変)。

鍋底は絶縁して、折れた取手のところでアースを取ります。
これでも結構苦肉の策です。

そして溶接。
溶加棒はちょっと特殊です(ニッケルの含有量が多い)けど溶接作業自体はそんなに特殊ではありません(母材の希釈は少なくします)。
溶接は表面だけでなく、開先を取ってしっかり溶接しています。
そうしないと強度が出ません。

溶接が終わればサンダー仕上げ、#60とその後は#120で仕上げています。
取手なので、触り心地は重要ですから滑らかに仕上げます。

こんな感じに仕上がりました。
この後に塗装です。
食品関係ですので、有機溶剤は基本ダメですけど、取っ手の部分限定ということで了承を頂きました。

鍋の中に塗料が入らないようにしっかりマスキングします。

同じ色の塗料は持っていないので、当社にある「赤」と「オレンジ」で重ね塗装しながら色合わせ。

そして完成!
ちゃんと出来るとホッとします。
出来ないときは落ち込みます。
このお鍋がまた楽しい食卓で活躍しますように。